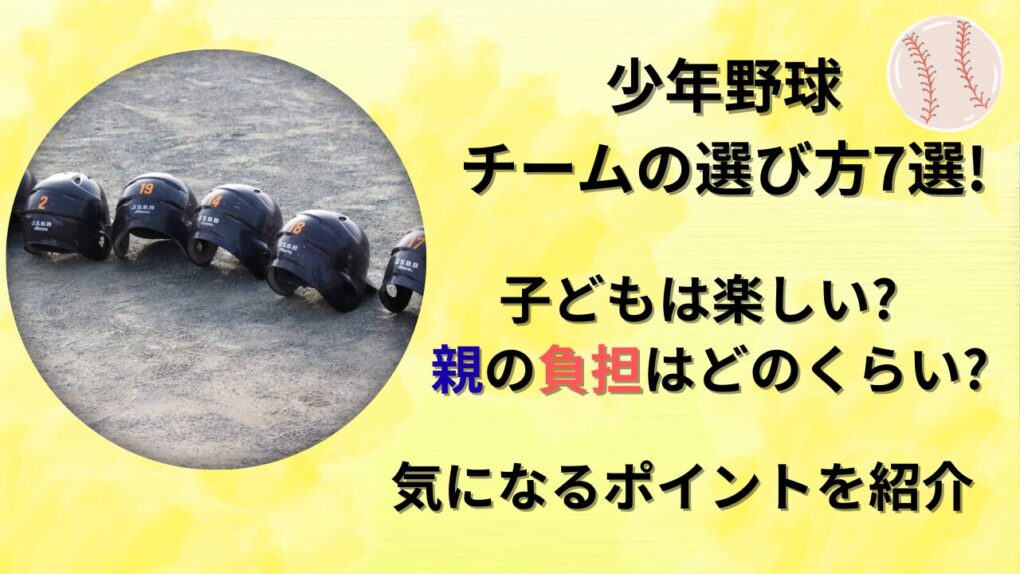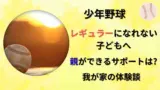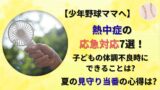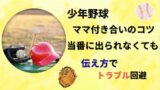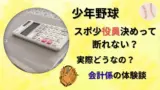子どもが野球をやりたいって言い出したけど、どんなチームに入ったらいいんだろう?
子どもが「野球をやってみたい!」と言い出したとき、
まず親として悩むのが「親の負担が少ない少年野球チームをどうやって選べばいいの?」という点ではないでしょうか。
でも、初めてだと分からないことばかりですよね。
私も、長男が1年生のとき「野球をやりたい!」と言い出し、何が分かってないのかも分かっておらず、保護者としても完全に初心者でした。
体験や見学には何度か行ったものの、説明を受けたつもりでしたが、いざ入ってみると「もっと確認しておけばよかった…」と思うことがたくさんありました。
ただ、いろいろな経験を経て、今では「このチームでよかった!」と心から感じています。





野球を始めるときに大切なのは、子ども自身が楽しめるかどうか。
そして、親の負担がどのくらいか知ること。
親子ともに、続けやすいチームを選びましょう。
親の負担は、当番や役員のサポート面、金銭面など様々です。
この記事では、私の体験や反省も踏まえて、実際に親の負担はどういうものがあるのか、
また、子どもが楽しく続けられる少年野球チームを選ぶための7つのポイントをご紹介します。





ちなみに、「少年野球」と一言で言っても実はこんな違いがあります。
- 学童野球 → 小学生の軟式野球(この記事の対象)
- 少年野球 → 中学生の軟式野球
- リトルリーグ → 12歳以下の硬式野球
- リトルシニア → 中学生対象の硬式野球
こちらは、小学生の「学童野球」を対象にした記事です。
一般的に検索では「少年野球」と調べる方が多いため、本記事では「少年野球」という表現を使用しています。
なお、学童野球のチームは、「スポーツ少年団(通称:スポ少)」という、日本スポーツ協会が運営する団体に所属していることが多く、そのため「スポ少野球」と呼ばれることもあります。





長男のチームも、スポ少野球です。
少年野球に入る前に|親子で話し合いたい「なぜ始めるのか」
長男が野球チームへ体験・入部するとき、
監督やコーチが、私たち保護者や子どもに伝えてくれたことがあります。
「少年野球の目的は、野球を通じて心身やスポーツマンシップを養い、健全な体をつくっていくこと。」
「礼儀や責任感、思いやりなどの心を育むこと。」





野球をやるならば、うまくなったら嬉しいです。
でも、それ以上に、子供時代に人として大切なことが身につき学んでいけたらいいなと思いました。
少年野球チームの体験練習に参加しよう!初心者が準備すべきこと
近くの少年野球チームを探す方法|Googleマップ&地域SNSの活用法
我が家の長男は、野球チームに入っている友人の紹介で体験参加させてもらうことから始めました。





知人紹介がない場合は、どうやって体験に参加すればいいのだろう。
「小学生 野球チーム ○○(地域)」などで検索すると、
どんなチームがあるのか情報が分かります。
まずは気になるチームのホームページをチェックしてみると良いです。
そして、そのサイトのメッセージ機能などを使って連絡を入れましょう。
その後、担当者と連絡を取り合い、見学・体験希望ができるように進めていきましょう。





最近では、インスタグラムで練習風景など写真や動画を載せているチームも多くあります。
体験・見学で注目すべき3つの視点|練習内容・雰囲気・指導者
実際に、体験では、お客様として迎えられます。
基本的に、厳しいことを言われることはありませんし、楽しく参加できる雰囲気があると思います。
子どもによっては、最初からスムーズに参加する子もいれば、緊張して保護者から離れて参加するのが不安になることもあります。
野球は好きだけど、周りの雰囲気に圧倒されてしまう場合もあるのです。
そんなときは、子どもの様子を見ながら、参加できるタイミングを待ちましょう。
焦らなくて大丈夫です。
子ども自身も周りをよく見ていて、雰囲気に慣れてくると心の準備ができてから参加することも多いです。





そういうときにも、指導者や周りの保護者たちがどんな風に接してくれるか感じることができます。
- 他の子がどんな様子で参加しているか見ておきましょう。
- 監督やコーチたちがどんな声掛けをしているのか、チェックする。
- チームの保護者たちが、指導者や子どもたちと、どのくらいの距離感でいるのかも見ておくと良いです。
初心者向け!少年野球チーム選びで失敗しない7つのポイント
1、うちの子に合う?指導スタイルを見極めよう





子どもの性格や目的に合う指導スタイルを見極めるのが、まず一番大切です。
厳しくても上手くなりたい?
のびのび楽しくやりたい?
実力主義で競争しつつ勝利をめざす?
試合は平等に全員が出られるスタイルがいい?
いろんな考え方があると思います。
自分でもどういうスタイルが良いのか分からないということもありますよね。





体験する日以外にも、普段の練習を見に行くこともおすすめします。
違和感を感じることがないかを確かめましょう。
<我が家の体験談…叱る場面もある>
長男の所属するチームでは、低学年と高学年で練習が分かれています。
休憩時はみんなニコニコしています。
練習になると、低学年はのびのびとやっていますが、高学年は緊張感をもって取り組んでいるなと感じます。
指導者が注意したり叱ったりする場面もあります。
怒鳴って聞こえることもあります。
でも、根底に愛情を感じます。





それは見学でも分かり、納得していました。
<我が家の体験談…実力主義のチーム>
また、高学年になると試合が多くなりますが、学年にとらわれず実力主義です。勝つためです。
長男も5年生のときに、4年生がレギュラーになって自分が外されたりすることもありました。
でも、本人がなぜなのかを理解していて、その頃から自主的に素振りをするようになりました。
そうして、ヒットを打って打点になったときに、監督からグータッチしてもらう経験ができたことで吹っ切っていました。
本人なりに前に進んでいます。
毎回レギュラーで外されない子もいます。
でも、長男のように外されることもあると思って取り組んでるケースもあります。
レギュラーになれていたとしても、自分が体調不良で休んだときに代わりに出た子が活躍すると次からはその子がレギュラーになることもありました。
母として複雑な心境のときもありましたが、長男のチームでは指導方針への口出しは厳禁。
実力主義のチームでは、こうしたことも珍しくありません。





正直、息子が1年生で野球を始めた頃、私は「チームが実力主義」かどうかなんて考えてなかったです…
多少の厳しさは聞いていましたが、実際に実力主義の世界を経験すると、親としても戸惑うことはありました。
でも、子どもが成長していくのに、いいチャンスであるという考え方もあります。
チームによって
「実力主義で競争しつつ勝利をめざす」
「みんな平等に出場機会を与える」など方針が分かれます。





お子さんの性格に合うスタイルを見極めましょう。
実際に、野球を続けていく過程で、途中で別のチームへ移る子もいます。
人によってそれぞれの感覚があると思います。
もし、親として、この雰囲気、この叱り方、このやり方は違和感があるな…
そう思ったとしたら、その感覚を大切にしてください。
厳しさもありつつ、優しさもありつつ、そのバランスが子どもにとってちょうどよく感じられるかどうか。
実力主義で悩んだときの体験談をもとにまとめました。
少年野球|レギュラーになれない子どもへの親ができるサポートとは?
2、練習場所・時間・頻度|生活リズムに合ってるかチェック!





子どもが続けやすいかどうかは、練習スケジュールの相性も大切です。
例えば、
・平日は夕方に1時間程度の練習があるチーム
・土日は朝から夕方までしっかりやるチーム
など、チームによって違います。
<長男のチーム:スケジュール例>
・土日祝日
・朝9時~夕方5時まで
→グランドがとれていないときは、午前か午後の半日になることも。
→夏や冬は、時間が短くなることが多い。
・練習場所→徒歩圏内の小中学校グランド





結構、がっつりですよね。
よくやってるな~と思います。
<我が家の体験談>
・練習場所が近いと、何かあったときにすぐ駆けつけられる点は本当に助かっています。
・土日祝日が活動日ですが、家族で出かけるなど予定があるときは、休みやすい雰囲気です。
・練習時間が長めですが、始めたばかりの頃は、あまり体力もなかったので、半日だけの練習にさせてもらうこともありました。





無理をせずに、子どものペースに合わせて、スケジュールの調節がしやすいかどうかも聞いてみましょう。
・家庭のライフスタイルに合っているか
・兄弟の習い事との兼ね合いはどうか
現実的に通えるかを考えることも重要です。
3、親の負担が少ないチームかを見極めよう|当番・係・頻度のQ&A
なんでお当番って必要?





少年野球は、当番があるイメージで大変そう。
保護者として、当番があるかどうかって気になるポイントですよね。
そもそも、当番とはどんなことをするのでしょうか?
<主に2点>
・監督やコーチにお茶や水などの用意をする
・ケガや体調不良の子に対応する
当番があるチームもあれば、当番がないチームもあります。
当番がないチームは、コーチが中心にその役割を担ってくれています。
コーチが部員のお父さんであるケースが多いです。
結局、親のサポートがないと成り立たないのが現実です。
少年野球チームの指導者は、ほとんどボランティアです。
普段は別の仕事をしていて、休日に無償で子どもたちに野球を教えてくれているのです。





無償でやってくれていることを知り、当番の仕事として、指導者の方へ飲み物などを用意することは納得できました。
そして、暑い夏は特に、水分が足りなくなる子もいますし、体調不良の子が出るケースも多いです。
万一の時に備えて、子どもたちを見守る人が必要なのです。
スポ少野球では、無償で教えてくれる指導者の方々、そして、親のサポートが不可欠です。
夏の見守りママに役立つ応急対応をまとめました。
お当番の内容・頻度は?





チームによって違うので、体験や見学のときに確認しましょう。
<長男のチーム:お当番例>
・班ごとに、月に2~3回お当番の日がある。
(1つの班に5~6人)
・各家庭の事情に合わせて、お当番に参加できる日や時間帯を班長へ連絡。
・指導者の方へ、お茶や水、昼食を買って用意する。
・ケガや体調不良になった子の対応をして、場合によっては保護者へ連絡。
・練習が終わった後、トイレ掃除をする。
・遠征時は、審判へ飲み物を渡すなど。
(長男が1年生で始めた頃→次男1歳、土日父親ほぼ不在)
ずっと付き添いをすることは難しかったので、参加できる時間を相談させてもらっていました。
子どもの成長とともに、以前よりは、参加できています。
お当番って行けない日はどうする?代替はある?





参加できないときがあってもいいのかな…
そう悩む人も多いのではないでしょうか?
もちろん、納得してもらえる理由があるのなら、参加できなくても仕方ないし、大丈夫です!
令和の時代、そう思う人は多いです。
<お当番に行けない理由例>
・仕事がある
・家族兄弟のスケジュールが重なってしまう
・下の子がまだ小さくて、預け先もなくずっといられない
・子どもの体調不良
・自分の体調不良





チーム体験のときに、当番来れない人もいるし、出来る人がやるという感じだから無理しなくて大丈夫。
とは、聞いていましたが…
実際、お当番に参加できないことで、気まずさを感じたりすることもあるかもしれません。
私もそういうときはあります。気になるのは、周りの反応…





あの人いつも来ないじゃない…
そんな風に思われるケースも防ぎたいって思ってます。
なるべく保護者同士のトラブルは避けたいもの。
だから、理由を伝えて、参加できるときは参加する姿勢を見せることが大切です。





長男の所属チームは、平和的な雰囲気があります。
<我が家の体験談:感謝の気持ちを大切に。>
「みんながそれぞれ周りへ感謝の気持ちを伝えていきましょう。」
長男がチームに入った頃に、先輩ママさんから言われたことです。
忘れてはいけないのが、自分が参加できないときに、負担してくれている人がいること。
我が家は、土日に父親不在のことが多く、下の子もいるため、日中ずっと参加し続けることは難しかったです。
お当番のときには、可能なタイミングで参加させてもらってました。
参加できないときは、申し訳なく思うことも多いです。
でも、長男が6年生になり、下の子の成長と共に、以前より参加できています。
下の学年のママさんが、以前の自分のような立場だったりすることもあります。
当然、理解できますし、雰囲気良くやりたいものです。
感謝の気持ちをしっかり伝えたり、できないときは無理せずに、やれるときには協力するという考え方が大切だと思います。
長男のチームでは、保護者の皆さんは温かく、困ったときには助け合おうとする風潮があるので本当にありがたいです。





保護者同士、相談しやすい雰囲気があるといいですね。
<保護者同士のトラブルを防ぐために>
・参加できない理由を伝える。
・周りに感謝の気持ちを伝える。
・無理はせず、参加できるときは参加するよう心がける。
少年野球のママトラブルを防ぐ工夫を紹介してます。
お当番以外にある係や役員って?
入ったばかりの頃に、当番以外のことをお願いされることはあまりないと思いますが…
実は、様々な役回りがあります。
・会長(キャプテンの親)
・副会長(副キャプテンの親)
・備品担当
・会計担当
・グランド担当
・スコア表の係(試合時)など…
スコア表の記入は、長男のチームでは書ける人がやってくれています。
私はできないので、本当にありがたいです。
チームによっては、当番にスコア表記入が入ってる場合もあるそうです。
<私の体験談:担当経験のある係>
会計担当→指導者への飲料代や備品代、遠征費、卒団式の準備費用など精算
発注担当→部の道具や部員のユニフォーム類などの発注
(検温表担当→コロナ渦で、部員や指導者の体温を検温表に記入)





家でできる事務的な仕事中心です。
練習や遠征に行くのが難しいことが多いのを考慮してくれてるのを感じます。
在籍期間が長くなると係や役員になることがあります。
少年野球の役員について体験談を添えて紹介してます。
4、通いやすい?親の送迎負担のチェックポイント
練習日の送迎で確認しておきたいこと
・近くても、保護者が送迎すべきなのか?
・自宅から遠い場合、送迎は可能かどうか。
・子どもが一人で自転車で通ってOKなのか?
野球は、道具や水筒など荷物も多いです。
安全のため、子どもが自転車で通うことがNGの場合もあります。
<長男のチーム:通い方>
自宅から徒歩圏内の子たちが多いです。
・慣れてくれば送迎なしでもOK
(低学年は親が送迎してることが多いです。)
・自転車→NG
チームによって、様々なので確認しましょう。
実際に、車が必要な距離でも強いチームへ通わせるために、親が送迎をする人もいます。
人それぞれなので、家庭での判断基準をもって考えるといいですね。
遠征・試合時の「車出し」って必要?
車だしとは、保護者が自家用車でチームの子供たちを練習場や試合会場へ送迎すること。
遠征がある場合、移動手段はどうなるのか。
電車や公共交通機関を利用するケースもあるかもしれませんが、
利用できない場所もあります。
自家用車を持たない家庭もあるので、遠征時の移動は、保護者やコーチが車だしをして移動するケースが多いです。
野球にかかわらず、サッカーやバスケチームでも同じです。
集団スポーツは、こうした保護者の協力が必要なのが現状です。





遠征での車だしは、心配事もありますよね…
・子どもが車酔いをして、車内を汚してしまったら…
・遠征先で、体調不良になってしまう子がいたらどうする?など
<長男のチーム:車だしの約束例>
・ユニフォームの上に、シャカパンをはくこと。
・各自、酔い止め対策をする。
・乗せてもらった際に、車内を汚してしまった。
→クリーニング代は汚してしまった子の家庭が負担する
(我が家では、コープ共済の個人賠償責任保険に入っています。)
・遠征先での体調不良→その保護者が迎えに行く
・ガソリン代として遠征費を出す(1㎞10円計算)
・車内で食べるの禁止
・お礼のあいさつを忘れないこと
このように、長男のチームでは、車だしに関してたくさんの約束事があります。
子どもを乗せるだけでなく、道具を運ぶための車だしもあります。
遠征時は特に、親の力なしでは成り立たないことを実感します。
自家用車の有無を伝えつつ、チームの車だし事情を確認しておくと良いでしょう。
5、少年野球にかかる費用はどのくらい?|会費・道具代を把握





野球を始めるにあたって、揃えるものがたくさんありそうで出費も多そう…
そうなんです。
野球は、道具やユニフォームの初期費用が、他のスポーツよりも結構かかります。
また、成長とともにサイズも大きくなり、買い替える必要が出てきます。
・必要な道具やユニフォームなどを確認
(グローブ・バット・帽子・試合用ユニフォーム・練習着・膝パット・ソックス・ベルト・スパイク・冬用シャカ・アンダーシャツ・シャカパンなど)





聞いてみると、おさがりをもらえる場合もあります。
最初は、譲ってもらえるものを使いながら、新しいものを徐々に揃えていく人が多いです。
一方で、
・部費や会費などの費用→チーム運営のために集めています。
(月ごとなのか、半年ごとかなど集め方や金額を確認しましょう。)
<長男のチーム:例>
1年間で合計→24,000円(一ヵ月にすると、2,000円)





一般的な習い事の月謝に比べると、安い方です。
6、チームの雰囲気はうちの子に合う?|在籍してる子やコーチの様子もチェック
体験や見学時に、自分の子以外にも、他の子どもたちの様子もよく観察しておきましょう。
・前向きな声を掛け合っている様子があるか
・どんな表情で取り組んでいるのか
・あいさつや礼儀などできているか
・仲は良くてもメリハリをもっているか など…
<我が家の体験談:仲間がいることで楽しめる>
長男は「仲間がいるっていいよね。」とよく言っています。
続けていれば、しんどいことはあるかもしれません。
ただ、一緒に野球をする仲間に励まされたり、感化されたり、仲間の存在があることは大きいです。





子どもが仲間と楽しんでいる姿を見れると嬉しいですよね。
7、他のチームも体験して比較しよう!
<我が家の体験談:1チームしか体験にいってない…>
友人の紹介だったので、知っている人がいて安心だということもあり、決める流れになったのですが…
正直、他のチームも体験していても良かったかなと思ったこともありました。
【理由は2つ】
・当番制が少し負担に感じてしまったこと
(他はどうなんだろうと思う時期があった…)
・実力主義のチーム方針に戸惑ったこと
親目線の理由ですが、
もっといろんな視点で、他も体験しながら、チーム選びをしていてもよかったなと思ったわけです。
結果的に、長男は一度も辞めたいと言ったことがないし、
しんどそうな時期も「つらいけど辞めたくはない!」と言って、
以前より楽しそうに続けています。
私自身も親として、チームの人間関係や雰囲気の良さを感じます。
みんなで、子どもたちを応援している感じがします。
だから今は、私もこのチームでよかったなと思っています。





後悔したり、チームに入ってから戸惑ったりしないように、他も体験することをおすすめします。
まとめ|親の負担と子どもの成長を両立できるチーム選びを
子どもが「野球をやりたい」と言い出したとき、
やらせてあげたいけれど…と、親としては悩むこともあるかもしれません。
少年野球を始めるということは、子どもだけでなく、保護者や家族にとっても大きな一歩です。
チームの方針、当番の有無、送迎、費用など、現実的に考えるべきことはたくさんあります。
たとえば、送迎事情ひとつ取っても、チームによって本当に様々です。
「車が必要な距離でも、強いチームに通わせたい」と送迎を頑張る家庭もあれば、
「送迎はできるけれど、お当番は難しい」と感じる人もいます。
親の負担の感じ方や許容範囲はそれぞれ違います。
だからこそ、各家庭で何を優先したいか、判断基準をもってチームを選ぶことが大切です。
「これなら頑張れる」
「ここは譲れない」
家庭に合った選択こそが、無理なく続けるためのポイントになります。
正直、続けていく中では大変なこともあるでしょう。
でもその分、子どもの頑張る姿に元気をもらえたり、成長を間近で感じられるのも、少年野球ならではの魅力です。
焦らず、納得のいくまで見学や体験を重ねて、
「ここなら安心」
「このチームに入れたい」と思える場所をぜひ見つけてください。
親子で一緒に、楽しく野球のある時間を過ごしていけたら嬉しいですね。
応援しています!
☆最後まで読んでいただき、ありがとうございました☆