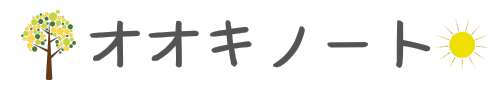長男が5歳の夏、初めてゴーヤを食べた日のこと。
食後、数時間してから、突然、全身に蕁麻疹(じんましん)が広がりました。
「一体、何が起きたの…?!」
驚きながらも落ち着いて考えてみると、
「普段食べないゴーヤをたくさん食べたこと」 しか思い当たりませんでした。
幸い、息子は元気で、蕁麻疹も2時間ほどで落ち着きました。
後日、小児科の先生に相談すると、
これは花粉アレルギーが原因だったことが分かったのです。
実は、花粉アレルギーと食物アレルギーには深い関係があります。
この時期になると、花粉症で悩む人も多いのではないでしょうか?

我が家は家族全員がアレルギー体質で、
花粉症の症状は春だけでなく、夏や秋にも出ます。
長男は1歳前後から目のかゆみや肌荒れが始まり、
5歳のときに血液検査でダニアレルギーと通年性の花粉アレルギーがあることが分かりました。
それから、少しでも症状を和らげてあげたくて、試行錯誤を繰り返してきました。
その中で、「花粉アレルギーは食べ物とも関係している」ということを知ったのです。
まずは、花粉アレルギーについて正しく知ることが、子どもの体を守る第一歩。
この記事では下記の内容を分かりやすくお伝えします。↓
・花粉アレルギーの基本知識
・子どもの症状を和らげるためにできること
・実際に効果を感じている花粉症対策
こんな方におすすめの記事です。↓
・花粉アレルギーについて詳しく知りたい。
・子どもの花粉症を少しでも和らげたい。
・効果的な対策や治療法を知りたい。

「知ることができてよかった」「これなら試してみようかな」
そう思ってもらえたら嬉しいです。
花粉症ってどんな病気?子どもにも増えている花粉症の原因とは
子どもに見られる花粉症の症状一覧
花粉症といえば「くしゃみ・鼻水・鼻づまり」のイメージが強いですよね。
でも実は、それだけではありません。
花粉が原因で、目や肌、呼吸器にもさまざまな症状が出ることがあります。
- アレルギー性鼻炎
- アレルギー性結膜炎
- 喘息(ぜんそく)
- アトピー性皮膚炎
1.アレルギー性鼻炎(くしゃみ・鼻水・鼻づまり)
花粉を吸い込むことで、鼻の粘膜が過敏に反応し、症状が出ます。
2.アレルギー性結膜炎(目のかゆみ・充血・涙目)
目に花粉が付着すると、かゆみやゴロゴロ感、充血などの症状が現れます。
3.喘息(ぜんそく)(咳・息苦しさ・ゼーゼー音)
花粉が気道に入り、アレルギー反応を起こすことで、咳が出たり呼吸がしにくくなることがあります。
4.アトピー性皮膚炎(肌のかゆみ・湿疹・乾燥)
花粉が肌に触れることで、かゆみや湿疹、肌荒れが悪化することも。
特に、汗をかきやすい季節や乾燥しやすい冬場は注意が必要です。
このように、花粉症の症状は「鼻」だけではなく、目・のど・肌にも影響を与えることがあります。
「いつもの肌荒れや咳が、実は花粉の影響だった」というケースも少なくありません。
まずは、子どもの症状が花粉によるものなのかを知ることが大切です。
症状の原因を知るためには、アレルギー検査を受ける方法があります。
病院で血液検査や皮膚テストを行うことで、どの花粉に反応しているのかが分かります。
花粉症はなぜ起こる?アレルギー反応の仕組みをわかりやすく解説
花粉症とは、スギなどの植物の花粉が原因で起こるアレルギー疾患のことです。
私たちの体には、異物から体を守る仕組み(免疫)があります。
「免疫力をあげていこう!」という言葉をよく耳にしませんか。
<免疫力>
人間の体は、異物(抗原)が入ってくると、それを排除するために抗体を作ります。
抗体は、異物を攻撃して体を守る働きをします。
免疫力は、体を守る働きをする大切な仕組みです。
抗体は、本来、体を守るために異物を攻撃します。
しかし、アレルギー体質の人は 「敵ではないものまで敵だと勘違いしてしまう」 ことがあります。
例えば、
花粉は本来、体に害を与えないものですが、
免疫が「これは危険なものだ!」と誤認し、全力で排除しようとするのです。
その結果、くしゃみ・鼻水・目のかゆみといった症状が出てしまい、本来なら必要のない反応で体がダメージを受けてしまうのです。
これが、花粉に対して起きている「アレルギー反応」です。
花粉症自体は遺伝しませんが、アレルギーになりやすい体質は親から子へ受け継がれることがあります。
花粉症が悪化する?シーソー理論で見る体のバランスとは

少し難しい話になりますが、
「花粉を浴びる機会が多いほど、花粉症が悪化してしまう」というお話です。
免疫の仕組みには、Th1とTh2という2つのバランスがあります。
- Th1:ウイルスや細菌と戦う力
- Th2:アレルギー反応を起こす力
健康な人は、このTh1とTh2がシーソーのようにバランスよく保たれています。
しかし、花粉症の人はTh2側にシーソーが大きく傾いている状態です。
すると、花粉という「本当は害のないもの」に対しても、免疫が過剰に反応してしまうのです。
さらに、花粉をたくさん浴びることで、Th2がさらに優位になり、症状が悪化しやすくなります。
つまり、花粉が多くなると、シーソーがどんどんTh2側に傾くイメージです。
このバランスを崩さないためにも、花粉をなるべく避けることが大切です。
花粉が多く飛ぶ日や時間帯は?
- 昼前後(10時〜14時)夕方(16時〜18時)
- 晴れて気温が高い日
- 空気が乾燥して風が強い日
- 雨上がりの翌日
花粉の飛散する時期は、花粉の種類によって違います。
スギ・ヒノキだけじゃない!花粉の種類と季節ごとの飛散時期
花粉症の原因となる花粉は、スギ以外にもあります。
地域によって飛散時期は多少ズレますが、
以下の表で、代表的なものをまとめました↓

↓表のマーカー部分は、我が家の長男がアレルギーをもっている花粉です。
| 樹木花粉🌳 スギ、カバノキ科(ハンノキ) | 2月~4月 |
| 樹木花粉🌳 ヒノキ | 3月~5月 |
| 樹木花粉🌳 カバノキ科(シラカンバ) | 4月下~6月 |
| 雑草花粉🌾 イネ科(カモガヤ、オオアワガエリ) | 4月中~6月/8月~10月 |
| 雑草花粉🍃 キク科(ブタクサ、ヨモギ) | 8月~9月ピーク~10月 |
| 雑草花粉🍃 アサ科(カナムグラ) | 9~10月 |
花粉症の約70%はスギ花粉症だと考えられています。
引用元:https://allergyportal.jp/knowledge/hay-fever
これはわが国には全国の森林の18%、国土の12%をスギが占めているためでもあり、関東や東海地方ではスギが中心になります。
また、関西ではスギと並んでヒノキも植林面積が広いため、ヒノキも要注意です。
一方、北海道にはスギやヒノキが少なくシラカンバ属(カバノキ科)が多いという特徴があります。
我が家の長男は、シラカンバ花粉アレルギーが100%という検査結果でした。
シラカンバ花粉症は北海道の方で多いそうですが、関東でも、シラカンバ花粉が飛ぶことはあるようです。
また、シラカンバ花粉症を持つ人は、ハンノキ花粉にも反応することがあります。
そして、スギ花粉症を持つ人は、ヒノキ花粉にも反応しやすいと言われています。
構造が似ているため、このようなつながりが起きていると考えられています。
口の中がかゆい?花粉症と関連する口腔アレルギーに注意
口腔アレルギー症候群とは、食べ物に含まれるアレルギーを起こす原因物質(アレルゲン)が、口の中の粘膜に触れて起こるアレルギー反応です。
口の中に、かゆみや腫れなどが起こります。
多くの場合、しばらくすると自然におさまります。
口腔アレルギー症候群は、花粉症の人に多く見られます。
花粉症の人が、特定の食べ物を摂取すると、アレルギー症状が現れることがあります。
花粉のアレルゲンと、一部の果物や野菜に含まれるアレルゲンが似ているため、アレルギー反応が起こるのです。
花粉の種類によって原因となる食べ物が変わってきます。
以下に、花粉の種類ごとに、反応しやすい食べ物をまとめました。↓
- スギ・ヒノキの花粉症を持つ人
トマト - カバノキ科/ハンノキ・シラカンバの花粉症を持つ人
バラ科やマメ科の食べ物、リンゴ、洋ナシ、サクランボ、モモ、スモモ、アンズ、アーモンド、セロリ、ニンジン、ジャガイモ、大豆、ピーナッツ、ヘーゼルナッツ、キウイ、マンゴー、シシトウガラシなど… - イネ科/カモガヤ・オオアワガエリの花粉症を持つ人
ウリ科の食べ物、メロン、スイカ、トマト、ジャガイモ、キウイ、オレンジ、ピーナッツなど - ブタクサ の花粉症を持つ人
ウリ科の食べ物、メロン、スイカ、ズッキーニ、カンタロープ、キュウリ、バナナ - ヨモギの花粉症を持つ人
セリ科の食べ物、セロリ、ニンジン、マンゴー、
香辛料(マスタード・コリアンダー・クミンなど)
すべての食べ物にアレルギーが起こるわけではなく、多くの場合、一部の食べ物に対してのみ反応します。
冒頭でもお伝えしましたが、
長男は、ゴーヤを食べて、全身に蕁麻疹が出たことがあります。
小児科の先生に相談しました。

先日、ゴーヤを食べて、全身に蕁麻疹が出ました。
ゴーヤアレルギーってあるんですか?

ゴーヤのアレルギーは稀なケースかもしれないけど、
ブタクサやイネ科の花粉アレルギーを持っていると、ウリ科の食べ物に反応することがありますよ。
ゴーヤを食べて全身に蕁麻疹がでるケースは珍しいようでしたが、花粉アレルギーと食べ物に関係性があるのだと分かりました。
長男は、トマト(スギ・ヒノキ)やピーナッツ(ハンノキ・シラカンバ・イネ科)に対して、アレルギー検査でわずかに陽性反応が出ています。
実際に、トマトやピーナッツを食べた後、症状が出ることはありません。
アレルギー反応が出た場合、症状が軽いからといって食べ続けると、重症化する可能性があるため注意が必要です。
今日からできる!家庭での子ども向け花粉症対策8選
家に花粉を持ち込まない工夫とは?玄関・洗濯・換気のポイント

なるべく部屋の中にも花粉を入れないように、
家族で取り組めると効果的です。
- 外出時は、マスクやメガネなどをする。
- 外出時は、帽子をかぶる。
(髪の毛に花粉がつかないように。) - 花粉が付着しにくいサラサラした素材の服装にする。
- 外出時は、花粉がついているアウターを部屋に持ち込まない。
(ウェットティッシュなどで拭くのも効果的) - 服についた花粉をはたいてから家に入る。
- 手洗い、うがい、顔洗いをする。
- 洗濯物や布団の外干しは控える。
- 空気を入れ替えて喚起をした後は、掃除をする。
花粉をできるだけ体内に入れない工夫が大切です。
部屋にも花粉を入れないように心がけましょう。

花粉の時期に、外に布団を干すのをためらってしまうことがあります。そんなとき、布団の宅配クリーニングは、とても便利です。
外遊びが大好きな子に!虫取りと花粉症の意外な関係
長男は、小学低学年のとき、夏に虫取りに行くのが好きでした。
夏といえば、イネ科花粉!!
イネ科の植物あるところに、虫あり…といった感じでしょうか。

イネ科花粉アレルギーの長男にとって、
虫たちのいる場所はアレルゲンだらけ…
長男は、バッタやチョウチョなどがいる草が生い茂っている場所へ行き、
汗びっしょりで帰ってきていました。
夏の時期は特に、長男は汗かきということもあり、肌荒れがひどかったです。
帰ってきたら、全身シャワーを浴びさせて、保湿をして着替える。
こうすることで、家の中に花粉があまり入らないように、なんとか症状の悪化を防いでいました。
アレルギーをもつ花粉のある所に行かないのが一番なのですが…
虫取りは、子どもにとって大事な自然体験なので、やらせてあげて、できる限りのケアをしていました。
花粉を洗い流し、シャワーのあとしっかり拭いてから保湿クリームを塗ってあげる。
花粉症の薬はいつ飲むのがベスト?効果的なタイミングを解説
花粉症の治療薬は、早い段階から飲み始めることで症状の悪化を抑えられることがわかっています。症状が軽いうちは粘膜の炎症も進んでいないため、早く治療を始めるほど、症状の改善が早まることが多いようです。
引用元:https://kateinoigaku.jp/qa/6690
花粉情報をもとに、花粉がたくさん飛ぶようになる少し前から、薬の服用を始めると効果的です。
私は、毎年2月に入ると目が痒くなりだし、鼻がムズムズするので、少し体の変化を感じたら、早めに薬を飲むようにしています。
以前は、症状が悪化してから薬を飲んでいたのですが、副鼻腔炎になってしまったことがあります。
副鼻腔炎とは、鼻の奥にある副鼻腔に炎症が起こり、膿がたまる病気です。アレルギー性鼻炎が長引くと、鼻の粘膜が腫れて副鼻腔の排出がうまくいかず、粘液が溜まることで細菌が増殖してしまう状態です。
副鼻腔炎は、悪化すると手術が必要となる場合もあります。

私は、3ヵ月通院して完治できましたが、とてもつらい思いをしたので、早めに対処することを心がけています。
毎年、花粉症でつらいという方は、少し早めの時期から耳鼻科へ行ったり、薬を用意しておくことをおすすめします。
薬によっては眠くなってしまったり、副作用の影響が出るものもあるので、自分に合うものを処方してもらいましょう。
花粉症治療の選択肢まとめ|症状や年齢別のおすすめ治療法
子どもに使える花粉症の薬とは?
薬物療法とは、アレルギー症状を抑えるために薬を使用する治療法です。
内服薬(抗ヒスタミン薬・抗ロイコトリエン薬など)
点鼻薬(ステロイド点鼻薬など)
点眼薬
アレルギー反応を抑制する注射薬(生物学的製剤)があります。
症状をすぐに抑えることができますが、アレルギー体質そのものを改善する治療ではありません。
根本治療を目指す!子どものスギ花粉症に舌下免疫療法という選択肢
<アレルゲン免疫療法>
皮下免疫療法→アレルゲンを皮下に注射する。
舌下免疫療法→舌下にアレルゲンを投与する。
アレルゲン免疫療法とは、アレルゲンを少量ずつ体内に入れていき、アレルギー反応が起こりにくい体質へ改善する根本治療です。
現在、スギ花粉とダニアレルギーの方に効果的な薬があります。
スギ花粉症やダニアレルギーでお悩みの方には、おすすめの治療法です。
また、注射による皮下免疫療法よりも、痛みを伴わない舌下免疫療法は、子どもも続けやすいです。

我が家の長男も、舌下免疫療法によって症状が改善しています。
詳しくは関連記事をご覧ください。
重度の花粉症には手術療法も?適応ケースとリスクを解説
手術療法とは、鼻の粘膜を処置することで花粉症の症状を和らげる治療法です。
代表的なものに、炭酸ガスレーザーを使って鼻の粘膜を焼く「鼻レーザー手術」があります。
即効性があり、薬を使わずに症状を軽減できますが、効果は1~2年程度で徐々に元に戻るため、定期的な施術が必要です。
鍼灸治療
花粉症に有効なツボを刺激することによって、症状を改善します。
レンコンが花粉症に効くって本当?話題の栄養成分とは
レンコンに含まれる抗アレルギー成分とその働きを解説

花粉症の薬を飲んでも、症状が気になってなかなか寝付けない…
体調によっては、そういうときもありますよね。
そんなとき、「蓮根(れんこん)」が体に良い効果をもたらしてくれるかもしれません。
昔から、蓮根の煮汁を飲んだり、しぼり汁を綿棒で鼻の奥に塗ると花粉症に良いと言われてきました。
最近では、蓮根の成分がアレルギー症状を和らげる可能性があるとも言われています。
我が家では、蓮根パウダーを利用しています。
無添加のものがおススメです。

蓮根に含まれる成分と効能をまとめました。
よかったらご覧ください。
- ビタミンC
→免疫バランスを整え、花粉症の過剰反応を抑えるのに役立ちます。
また、ビタミンCは熱に弱いですが、蓮根の主成分でんぷん質が守ってくれるため、加熱しても失われにくいのが特徴です。 - 食物繊維
(水溶性と不溶性両方の食物繊維を含んでいます。)
→腸内環境を整え、免疫力アップをサポート! - カリウム
→体の塩分バランスを整え、むくみ予防にも。 - ポリフェノールの一種であるタンニン
→抗炎症作用があり、花粉症による鼻の粘膜の腫れやかゆみを抑える効果が期待できる。 - 鉄分
→血液を作る成分。疲れにくい体を作る手助けになります。 - ムチン
→粘膜を保護し、のどの炎症をやわらげる。
知人から「蓮根パウダーは、鼻やのどの粘膜にとてもいい。」と聞き、
使い始めたのですが…
実際、痰が絡んだり咳が出て寝付けないときに、蓮根パウダーを溶かして飲むと、不思議と落ち着いて眠れることが多くなりました。

薬を飲んでもおさまらないときや、できるだけ薬に頼りたくないときの自然なサポートとして、我が家では数年買い続けていて重宝しています。
子どもでも食べやすい!レンコンパウダーの簡単レシピ
ハチミツを入れてホットドリンクに
→ ハチミツには殺菌効果もあります。のどの炎症ケアにも◎
発酵食品のヨーグルトや納豆に混ぜる
→ 腸活&免疫力UPへ!
食事から体質を整えることで、花粉症の季節を少しでも快適に過ごせるかもしれません。
毎日の習慣に取り入れて、自然なケアをはじめてみましょう!
花粉症に悩むママへ。最後に伝えたいこと
正直、自分の子どもがアレルギー検査を受けるまでは、花粉症についてあまりよく知りませんでした。
私自身、中学生の頃から、アレルギー性結膜炎で花粉症だったのに。
なんで、花粉症になるのか…
原因を分かっていることが症状改善の一歩なのです。
子どもがアレルギー性結膜炎の症状で眼科を受診したとき、
「洗濯物は、花粉がつくから外に干してはいけない。症状が悪化していくから。」
と教えてもらいました。
「洗濯物は外で干したい…」という気持ちもありましたが、
中干しにしてみると、やはり症状が落ち着いていったのです。
外干しにしていた時より、中干しにしてからの方が薬も効いてる感じがしたのです。
そして、今まで花粉症対策を全然できていなかった…と振り返りました。
花粉に触れる量が多くなるほど、花粉症を悪化させてしまう恐れがあるということも分かっていませんでした。
花粉症についてよく知ることは、自分や家族にとって、とても大切なこと。
花粉症は、適切な知識と対策で症状を和らげることができます。
少しの工夫が、大きな違いを生むことも。
この記事が、花粉と向き合うヒントになれば嬉しいです。
☆最後まで読んでいただき、ありがとうございました☆