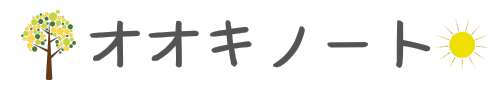もう無理…!夜泣きはいつまで続くの?
「なんでうちの子はこんなに夜泣きがひどいの?」
「どうしたら、夜泣きはなくなるの?」
毎晩続く夜泣き。
眠れなくてイライラするし、寝た!と思ったらまた泣き出す…。
何をしても泣き止まないと、「私の育て方が悪いのかな…」と、不安になり、自信をなくしてしまう。
私も同じでした。
我が家の長男は、夜泣きがとてもひどかった。
2歳ごろが夜泣きのピークで、3歳前後で落ち着いてきました。
今思うのは 「夜泣きは必ず終わる」ということ。
次男も夜泣きをしました。
でも、「終わりがくる」と知っていたから、少しだけ気持ちが楽だった。
それでも、夜泣きがつらくて何度も泣いた。
「泣きたいのはこっちだよー!」と叫んだこともある。
正直、精神的にボロボロだった。
あれから数年…
今では夜泣きしていた頃が懐かしくなるほど、子どもはぐっすり眠るようになりました。
この記事では、夜泣きで孤独を感じているママに向けて、
「大丈夫、終わりは来るよ」 というメッセージを伝えます。
この記事は、こんなママに読んでほしい。
- 夜泣きがつらくて孤独を感じてしまう。
- 夜泣きがいつまで続くのか、不安でたまらない。
- 良い夜泣き対策があれば試したい。
もし、いま夜泣きに悩んでいるなら…。
この記事を読んで、つらい気持ちが少しでもラクになってもらえたら嬉しいです。
【体験談】2歳半まで続いた長男の夜泣きと私のリアルな記録
生後8ヶ月から始まった長男の夜泣き|夜中の対応と葛藤
長男の夜泣きは、生後8ヵ月頃から2歳後半までありました。
生後6ヵ月くらいまでは、よく眠る子でした。
オムツは替えたばかりだし、お腹がすいてるわけでもない。
おかしいなという日が続いて、
「あぁ、夜泣きがはじまったんだ」と悟ったのです。
一歳を過ぎてからは、一段と大変でした。
夫は、いろんな面で協力してくれます。
ただ、仕事もあるので、夜中はなるべく休んでもらいたい。
主人には、別部屋で寝てもらうようにしました。
基本的には、夜泣きは私が対応しました。
しかし、どうしようもなく心が折れる時があります。
幼い息子も眠れなくて、どんどん泣いて、私もイライラして怒ってしまう。
朝になり起きてくる夫に、夜中しんどかったことを訴える日もありました。
出口が見えない真っ暗なトンネルをずっと歩いているような。
だから、夫が仕事のない日は、夜中に助けてもらうことも多かったです。
一人で対応しているよりも、夫婦で話をしていると息子は静かに眠っていくのです。
夫婦二人で対応していると、私も少し心穏やかになれました。
親が心穏やかになると、子供も穏やかに眠るようでした。
背中スイッチ対策!赤ちゃんが布団で起きない抱っこのコツ
夜中に急に大声でギャンギャン泣きだす!
泣き声が大きすぎて、早く静かにさせたいと思ってしまう。
抱っこひもをつけて、抱っこすると落ち着く。
これはもう寝たぞ~と思って、布団に寝かせると、再びギャンギャン泣き出す!
「背中スイッチ」と言われるこの現象に何度も心折れました。
1時間以上かけて、やっと布団で寝てくれた…と思って、自分も眠りにつくと、
30分も経たないうちに再びギャンギャン泣かれることもありました。
抱っこしながら座ると泣くから、ウロウロ歩く。
5~10分くらいウロウロすると、座っても泣かなくなります。
そうして、布団に寝かすと泣かれるから、しばらく抱っこしながらソファに座り、そのまま眠ったりしていました。
「いつまで続くんだろう…」
「何がいけないんだろう…」
何度も何度も心が折れそうになり、疲れすぎて涙が出てくるんです。
この「背中スイッチ」、
実は「お腹スイッチだった!」ということを知ったのです。
次男の夜泣き時代です。
私が見つけた記事とは違うかもしれないけれど。
↓下記の記事は、4児を育てるベテランママでもある黒田公美チームリーダー(脳神経科学)らによる国際研究チーム。
ベッドに寝かせる時、赤ちゃんが一番目を覚ましやすいタイミングは、背中を着けた時ではなく、実は抱っこしている親と密着していた「おなか」が離れる瞬間だということにも気づきました。
引用元:https://www.yomiuri.co.jp/otekomachi/20221212-OKT8T352967/
何と、「スイッチ」は背中ではなくおなか側にあった!
そこで私は、なるべく次男のお腹を離さないまま、寝かせるように心がけました。
お腹を離すときは慎重に、手のひらでお腹をしばらく優しくおさえて、顔も近づけて、ゆーっくり離れる。
長男の時よりも、失敗する回数が少なかった気がします。
赤ちゃんが夜泣きする理由とは?原因と発達の関係

夜泣きしない子もいるのに。
うちの子は夜泣きがひどくて、何が原因なんだろうか…
そんなことをふと思ったりしながら、毎日過ごしてました。
子育てをしながら、夜泣きは子供の成長段階で起きる自然なことだと分かってきました。
夜泣きは、体の変化や環境、睡眠リズム、体調、日中の刺激などが原因で起きています。
赤ちゃんの睡眠は、大人とはちがって発達段階にあります。
そのため、夜泣きが起こるのは、睡眠中に、その日に受けた刺激や情報を整理するのに、未熟な脳が覚醒し興奮してしまうからです。
睡眠と覚醒の切り替えがうまくできないのです。
また、赤ちゃんにも生まれつきの気質があり、これが夜泣きの有無に関係しています。
夜泣きがある子もいれば、夜泣きがない子もいます。
「夜泣きがひどい=育て方のせい」ではなく、赤ちゃんの生まれ持った個性によるものが大きいです。
赤ちゃんから幼児期は、急成長をしていきます。
夜泣きが始まるタイミングは、体の変化が起こる下記の時期が多いです。↓
生後4〜6ヶ月(睡眠の変化・寝返りの練習・歯が生え始める)
生後8〜10ヶ月(ハイハイやつかまり立ちの発達)
1歳前後~(言葉の発達・歩き始める)
赤ちゃんにとって、不快な原因があって夜泣きが起きていることもあります。
・お腹がすいている
・のどが渇いている
・オムツが蒸れている
・部屋が暑すぎたり、寒すぎたりする
・衣服や布団の肌ざわりが気になっている
・体調が良くないかもしれない
夜泣きの対応は本当に大変ですが、「成長しているんだね」という思いで向き合っていきましょう。
必ず終わる時期は来ます。
成長とともに、睡眠が深くなり、夜泣きが減っていきます!
自宅でできる夜泣き対策7選【環境・習慣・寝かしつけ】

「夜泣き対策で、どんなことができるのか」をまとめました。
- 生活リズムを整える
- 心地よい寝室環境を整える
- 寝る前のルーティーンを作る
1.生活リズムを整える
・朝起きたらカーテンを開けて光を浴びさせる
・夜は部屋を暗くする
・日中は外に出て体を動かす
・授乳や食事、お風呂はなるべく決まった時間にする
毎日、完璧にできるわけではないですね。
ママ自身が疲れているときは、子供と一緒に昼寝をゆっくりする日もあっていいと思います。
外に出たり、時間通りにできなくても、自分を責めることなく過ごしていきましょう。
2.心地よい環境を作る
・寝る前にはテレビや明かりを消して部屋を薄暗くする
・寝る前にオムツをチェックする
・室温が赤ちゃんにとって心地よいか確認する
・汗をかいて服が濡れているときは着替えさせてあげる
3.寝る前のルーティーンを作る
・「寝んねしようね」などの声かけをする
・寝る前に絵本を読むなど、毎日寝る前にすることを決める(入眠儀式を決める)
・寝かしつけ方法を頻繁に変えるのはやめましょう。
・授乳したまま寝付かせないようにしましょう。
同じ行動を繰り返すことで、赤ちゃんが『そろそろ寝る時間』と安心して眠りにつきやすくなります。続けやすいスムーズな流れにしていきましょう。
夜泣きを乗り越えるためのママの心構え3つ【自分を責めない】
- 夜泣きは、脳が急成長している証拠
- 必ず終わりは来る
- 助けてもらう
1.夜泣きは、脳が急成長している証拠
よく祖母に言われた言葉です。
「情報整理をしているから、頭がいいんだよ~。」
こんな風に言ってもらえたことが、支えになって乗り越えられました。
幼い子供の脳が急成長をしているから、夜泣きは起きている。
誰のせいでもなく、成長の証なんだと思って乗り切っていきましょう。
2.必ず終わりは来る
夜泣きは、寝不足やストレスが溜まり、本当にしんどいものです。
しかし、夜泣きは、必ず終わるときがきます。
我が家の子供たちは、2歳頃が夜泣きのピークで、だんだん減っていきました。
数年が経った今では、夜中に一度も起きずにぐっすり眠っています。
(風邪などひいてるときは起きるときもありますが…)
「あの頃は大変だったよね。」
そう懐かしく思う日が必ずやってくることを信じてください。
3.助けてもらう
家族に頼れるなら、子供を見てもらっている間に、自分が休ませてもらえると嬉しいですね。
夫婦で、役割分担を話し合い乗り越えていく方法があります。
でも、家族に頼ることが難しい状況もあります。
「自分がやらないといけない…」
そう思って頑張っていても、つらくて押しつぶされそうになる。
夜泣きの対応に疲れてしまったら、息抜きできる時間を確保できないか子育て相談をしているところに問い合わせてみるのもいいです。
子供を一時的に預けられる方法が見つかるかもしれません。
今すぐ泣き止んでほしい!実際に効果があった夜泣き対処法3選

夜泣きは、まず泣き止んでほしいですよね。
泣き止んでもらうために、やっていたことが3つあります。
- 音楽をかけた(子供が泣き止む曲を見つける)
- 場所を移動する
- 抱っこひもでおんぶ
1.音楽をかけた(子供が泣き止む曲を見つける)
長男のときは、ロック調の洋楽をかけると目を閉じて静かになることが多かったです。
次男のときは、反町隆史の「POIZON」をかけると効果的という話を聞き、試したところ、曲が始まると数秒で静かになっていました!
泣き止んで眠りに入ったところで、オルゴール調の音楽に切り替えたりして、寝かしつけていました。
2.場所を移動する
廊下や別の部屋へ移動することで、切り替わったりするときもありました。
ベランダに出て、外の音や空気を感じさせると落ち着きを取り戻すことも多かったです。
3.抱っこひもでおんぶ
おんぶをしながら、食器の片付けなどを始めると泣きやむことも多かったです。
静かになったなと思ったところで、スマホで検索したり、できる範囲で自分のしたいことをする時間として過ごしていました。
当時、好きなサイトを見つけて、子育てに役立つような情報や便利な商品を検索することが多かったです。

子育てに便利なアイテムに出会えるおすすめのサイトです。
その他にも、夜泣きを乗り越えるために、自分と子供に合ったやり方を探せるといいですね。
最後に伝えたいこと|育て方のせいじゃないということ
夜泣きするかどうかは、赤ちゃんの個性や成長段階によるものです。
ママやパパの育て方が悪いわけではないのです。
生活リズムや環境を整えることで、夜泣きを軽減できる可能性があります。
しかし、いろいろ工夫していても、夜泣きが続くときもあります。
幼い脳が刺激を受けているからこそ、夜泣きをするのかもしれません。
夜泣きが終わる時期は、個人差があります。
でも、大切なことは、子供が成長している証拠だと思って、焦らず見守ること。
「あのときは本当に大変だったな。」
そう懐かしく振り返る日は必ず来ます。
あともうひと踏ん張り。疲れも溜まって大変だと思います。
どうか体を大切に、息抜きも忘れずに。
長いトンネルを抜けるときが来るのを心から応援しています。
☆最後まで読んでいただきありがとうございました☆