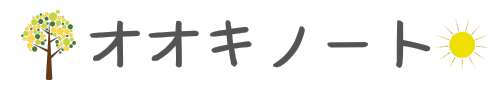寝不足で、心も体もしんどい
母乳で育てたいけど、完璧にできない…
ミルクを足すことに罪悪感を感じてしまう
「母乳が順調に出ているママを見ると、うらやましい。」
「母乳が出ない自分を責めてしまう」
そんなふうに悩んでいませんか?
母乳育児がしたいと思っていても、できないときがあります。
体質や産後の体調、赤ちゃんの吸いつきなど、理由はさまざまです。
産後は心身ともに不安定になりやすい時期。
母乳が出ないことやミルクを足していることに、罪悪感を感じることもあるかもしれません。
でも、赤ちゃんにとって、一番大切なことは何でしょう?
それは、「愛されること」です。
悩んでいるのは、赤ちゃんを大切に思い、愛情を持って向き合っている証拠。
母乳にこだわらなくても、愛情は十分に伝わっています。
他の選択肢、ミルク育児について知ることで、気持ちが軽くなるかもしれません。
こちらの記事では、混合育児や母乳からミルクへの移行について、前向きに考えるヒントをお届けします。
記事の内容は下記の通り↓
- 母乳からミルク育児になった体験談
- 母乳が出ないときの対処法/ミルク育児への切り替え方
- 母乳育児にこだわらない考え方/ミルクでも安心して育てられる知識
初めての産後、私は母乳育児をしたいのに、体が思うようにいかず、悩んでいました。
「完全母乳」この言葉にこだわりすぎて、自分を追い込んでしまっていたんです。
長男の産後は、母乳育児がうまくいかず、周りのお母さんたちが母乳で育てている姿を見るたびに、自己嫌悪に陥り、後ろめたさを感じていました。
でも、そんな私を救ってくれたのは、長男がミルクを飲んで、ニコニコ元気に成長する姿です。
その姿を見て、「母乳じゃなくても、赤ちゃんは元気に育つ」と気づくことができました。
次男の産後は、母乳で育てられなくなっても、母乳にこだわらずに、ミルク育児をすることに前向きになれました。
ミルク育児には、家族の協力を得やすかったり、赤ちゃんが満足そうに飲んでくれる安心感があることにも気づきました。
母乳育児は、誰もが自然とできることではありません。
でも、どんな育児方法を選んだとしても、お母さんが赤ちゃんの為に一生懸命に向き合っていることが大切なのです。
たとえ、母乳をあきらめたとしても、自信をもって進みましょう。
赤ちゃんは、育ててくれているお母さんが大好きです。
この記事を読んでくださった方が、
ミルクで育児をすることへの罪悪感が軽くなり、自信をもってミルク育児ができるようになるお手伝いができたら嬉しいです。
心から応援しています!
<我が家の子供たちの場合>
長男は、母乳とミルクの混合育児から、生後半年ほどでミルク育児へ
次男は、生後2か月から完全にミルク育児へ
長男の育児
NICUにいた長男
2014年3月 長男誕生
我が家の長男は、へその緒が首にからまって生まれてきて、
呼吸過多になってしまい、すぐにNICUへ連れられて行きました。
出産した日に、私は、直接授乳をすることはできませんでした。
だから、初乳は、助産師さんのサポートを受けながら、
昼も夜も、3時間おきに搾乳して届けてもらっていました。
初乳とは、分娩後、数日間に分泌される母乳のことです。
初乳には、赤ちゃんを病気から守る免疫物質がたくさん含まれています。
初乳の免疫効果は、特に生後1週間~1ヶ月の間に重要です。
微々たる量でしたが、
ミルクに初乳を入れて、赤ちゃんに飲ませてもらっていました。
翌日には、私は息子と面会ができるようになりました。
初めて、授乳を試みると、うまくできませんでした。

お母さんも授乳は初めてだし、
最初は、赤ちゃんもうまく飲めない子もいるんですよ。
がんばって練習していきましょう。
母乳で授乳をしたあとは、哺乳瓶でミルクを飲ませてあげます。

がんばれば母乳で育てられるようになるんだ。
こうして、母乳とミルクの混合育児が始まりました。
幸いなことに、
NICUにいた息子は、入院期間5日間で、母子一緒に退院できました。
- 最初から哺乳瓶でミルクを飲んで育っていた息子
- 哺乳瓶に慣れていた
- 私の乳頭が凹んでいるので飲みにくそうだった
- おっぱいはガチガチに張り、搾乳してた
- 授乳後、足りなくて口をパクパクして大泣きされる。
- ミルクを足すとよく飲んだ
低音型突発性難聴/ミルクで育てる
長男が生まれて二週間後の朝、
目覚めると、私の片耳は、音が二重に響いてよく聞こえませんでした。
受診結果は、低音型突発性難聴です。
突発性難聴とは
突然、左右の耳の一方(まれに両耳)の聞こえが悪くなる疾患。
一週間以内に治療を早めに開始することが望ましい。
ステロイドの薬を服用しなければならなかったので、母乳は与えられません。
それでも、母乳が出なくなるのは嫌だったので、搾乳は続けました。
搾乳しては捨てるを繰り返す。
だから、約一か月、息子は完全ミルクで育っていました。
家族のサポート
里帰り出産だったので、実家の母にサポートしてもらっていました。

睡眠をとって体を治すことが大事!
母乳にこだわらずに、ミルクいっぱい飲んでくれるからいいんじゃない。

それでも母乳で育てていきたい。
体は大変だけど、やめてしまうのもさみしい。
実家家族のサポートのおかげもあり、突発性難聴は完治できました。
そして、混合育児をまた始めました。
母乳育児を軌道にのせたくて、必死でした。
でも、しばらくおっぱいを吸ってもらえなかったのもあり、
母乳はあまり出るようにはなりませんでした。
一方、息子は、ミルクをよく飲むし、満足気なのです。
体重も順調に増えていました。

ミルクでもしっかり育つわよ。
そのうち離乳食が始まるから大丈夫。
実家の母は、おっぱいを嫌がる私をミルクで育ててくれました。
母乳でなくても飲ませることが一番大事だと知っています。
だから、自信をもって「ミルクでも大丈夫!」だと言ってくれたのです。
私の代わりに、赤ちゃんにミルクを与えてくれている母はとても幸せそうでした。
哺乳瓶でミルクをあげることは、ママ以外でもできます。
赤ちゃんにミルクをあげているとき、みんな心が温かくなりますね。
離乳食が始まるころには、
母乳に対するこだわりはほとんどなくなっていました。
- ミルクで育てている友達に会えて、気持ちが楽になった。
- ミルクは準備が大変だけど、ママ以外でもあげられる。
- 離乳食が始まると、離乳食の食べさせ方について考えるようになった。
次男の育児
母子同室
2019年5月 次男誕生
次男のときは、里帰りはしませんでした。
当時、長男は幼稚園の年長さん。
次男の産後はとても穏やかで、NICUへ行った長男のときと違い、母子同室でした。
初乳も直接飲ませてあげられました。
次男は、長男よりも飲む力が弱くて、飲みながら疲れてすぐ寝てしまう子でした。
赤ちゃんによって、個人差があるのだなと認識しました。

授乳はどうしたいですか?
母乳でお考えですか?

母乳で育てられたら母乳で、
無理はせずに、ミルクで足していきます
長男の時に、母乳にこだわらなくても良いと学んだので、
自分の体質も考えて、母乳が出なそうならミルクにするつもりでした。
でも、長男の時よりも母乳が出ているようでした。
次男の入院/搾乳した母乳を届ける
2019年7月(次男生後2か月)
当時、幼稚園で手足口病が流行していて、
長男が40度の発熱で感染してしまいました。
手足口病とは、
手のひらや足の裏、口の中などに水ぶくれのような発疹ができるウイルスです。発熱しない場合もあります。
発症の2日後、次男は授乳を嫌がり、ミルクもほとんど飲みません。
その夜、嫌な予感は当たり、次男は38度2分で発熱。
次男は、普段はベッドにいると自分で眠ってしまうような赤ちゃん。
しかし、高熱で苦しそうにうなり、
夜中まったく眠らず、主人と交代で抱っこを繰り返していました。
翌日、次男は、手足口病で入院となりました。
長男は解熱してましたが、全身の発疹がひどくて休んでいました。
だから、午前中、主人に仕事を休んでもらいました。

水分がとれていないので入院して点滴します。
お兄ちゃんもまだ大変なときなので、
入院の付き添いはなくても大丈夫ですよ。
お兄ちゃんのそばにいてあげてください。
搾乳した母乳を届けてもらえるといいです。

病院の売店で、
母乳を冷凍できるパックが売っています。
ミルクと哺乳瓶、哺乳瓶消毒、オムツや肌着の用意をお願いします。

分かりました。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
自宅へ戻り、荷物を用意して、病院へ届けました。
そして、次男には申し訳ないですが、長男のいる自宅へ帰りました。
その晩、私が38度の発熱。
胸がガチガチに張っていたけど、搾乳せずに、一晩眠って朝を迎えてしまいました。
一晩で熱は下がりました。
その後4日間、冷凍した母乳を持って、病院へ行きました。
次男は、だんだんミルクを飲むように回復しました。
退院後、やはり母乳よりもミルク中心の育児になりました。
完全ミルクへ移行
次男の退院後、背中から首にかけて激痛が走りました。
受診結果は、首の推看板ヘルニア。
次男の入院前に、長時間抱っこし続けた負担がきていました。
推看板ヘルニアとは
骨と骨の間にある推看板がとびだして神経を圧迫して、炎症し、痛みやしびれなど起こること。
推看板が負荷をかけて劣化することで、腰、背中、首に起きやすい。

ステロイド薬で治療していきます。
授乳中ですが、母乳をやめることはできますか。

はい。母乳やめられます。
よろしくお願いします。
こうして、生後2カ月の次男は、完全ミルクで育つことになりました。
飲み方にも個人差
長男の場合
- 激しく大泣きする
- 眠くても目をつむりながら、最後までゴクゴク飲み続ける
次男の場合
- 泣き方が激しくはない
- 眠くなって、そのまま飲むのをやめてしまうときがある
- 足をくすぐったりして、起こして飲ませることもあった
ミルクのあげ方に関しては、次男の方がいろいろ苦労しました。
しかし、二人ともよく食べる元気な子に育っています。
母乳でもミルクでも赤ちゃんは育つ。
大切なのは、無理をせず、自分の体と赤ちゃんの状態に合わせて柔軟に選択することだと感じました。
母乳とミルクの比較
メリット・デメリット
| 母乳のメリット | ミルクのメリット |
| (赤ちゃんにとってのメリット) ・赤ちゃんに最適な栄養バランス ・月齢やニーズに応じて成分変化 ・消化が良く赤ちゃんの腸に優しい ・抗体や免疫因子があり病気予防ができる (お母さんにとってのメリット) ・いつでも適温で準備不要 ・経済的 ・産後ママが痩せやすい ・生活習慣病のリスクが下がる ・子宮収縮を促し、産後の回復を早める | (赤ちゃんにとってメリット) ・必要な栄養素が含まれている ・一定の栄養バランスが保たれている ・腹持ちがいいのでよく眠れる (お母さんにとってのメリット) ・人前でもあげられる ・ママ以外の人が授乳できる ・赤ちゃんが飲んだ量が分かる ・カフェイン入り、アルコール、薬など気兼ねなくとりやすい ・赤ちゃんを預けやすい ・スケジュールを調整しやすい |
| 母乳のデメリット | ミルクのデメリット |
| ・カフェインやアルコールの摂取を制限する必要がある ・薬の服用も制限が必要 ・母親以外の人が授乳できない ・長時間赤ちゃんと離れにくい ・授乳量が分かりにくい ・母乳を与える場所に制限があることもある ・母乳パッドや搾乳器など育児用品を必要とする場合がある | ・抗体や免疫効果はない ・母乳に比べて消化に時間がかかる ・調乳のための時間や手間がかかる ・温度管理や衛生管理が必要 ・外出時に、調乳用のお湯や哺乳瓶の準備が必要 ・ミルク代かかる ・哺乳瓶や消毒用品が必要 ・アレルギー反応を示す場合もある (アレルギー対応のミルクがあります) |
赤ちゃんの免疫について

ミルクには、抗体や免疫効果がないと聞くと不安になります。

でも、大丈夫です。
免疫はミルク育児でも赤ちゃん自身が作り出すようになります。
実は、私が母乳にこだわっていた理由の一つは、
抗体や免疫がミルクにはないと引っかかっていたからです。
しかし、母乳に含まれる免疫因子は、生後すぐの赤ちゃんを病気から守る大切な役割を果たしますが、その後は赤ちゃん自身が免疫力を育てていきます。
赤ちゃんの免疫システムは、生後3~6ヶ月頃から本格的に発達を始め、
赤ちゃん自身が自分で抗体(特にIgG抗体)を作り始めるようになります。
赤ちゃんの長期的な免疫力は、自分の体が作るものです。
適切な栄養と清潔な環境、予防接種などを行えば、ミルク育児でも健康な免疫システムを育むことができます。
☆予防接種は医師と相談しながら適切なタイミングで受けましょう。
☆赤ちゃんが触れるおもちゃや哺乳瓶は、定期的に消毒を心がけると良いでしょう。
このように、赤ちゃん自身も免疫力を自分で育んでいけることを知り、不安が和らぎました。
母乳育児は母子にとって素晴らしい体験ですが、無理をせず、家庭の状況や母親の体調に合わせた選択をすることが大切です。
母乳がでないと感じる理由4つ
1,ホルモンバランスの乱れ
母乳の分泌には、ホルモン(特にプロラクチンとオキシトシン)が大きく関与しています。
このホルモンバランスが乱れると、母乳の出が悪くなることがあります。
2,ストレスや睡眠不足
ストレスや睡眠不足は、
母乳を出すホルモンであるオキシトシンの分泌を妨げます。
- ストレスの原因
- 育児の不安やプレッシャー
- 周囲からのサポート不足
- 初めての母乳育児での痛みや悩み
- 対策
- 家族やパートナーにサポートをお願いする。
- 短時間でも良いので休息を取る工夫をする。
- リラックスできる音楽を聴いたり、深呼吸をする。
3,赤ちゃんの飲み方が浅い
赤ちゃんが母乳を飲むときに、
乳首を深くくわえられていない場合、母乳がしっかり出なくなることがあります。
- 原因
- 赤ちゃんが乳首の先端だけをくわえている
- 赤ちゃんの口の形や舌の使い方に問題がある場合(例:舌小帯短縮症)。
- 対策
- 助産師や母乳育児相談の専門家に相談し、赤ちゃんの授乳姿勢やくわえ方を確認してもらう。
- 授乳クッションを使い、赤ちゃんを正しい高さで抱く。
4,母乳不足のサインと勘違いしていることもある
赤ちゃんが泣いて、頻繁に授乳を求めてきたり、授乳後も満足していないように見えることもあります。
そこで、母乳が足りていないと勘違いしてしまっていることもあるのです。
しかし、実際には以下のような場合、母乳は足りている可能性が高いです。
<母乳が足りているサイン>
- 赤ちゃんの体重が順調に増加している(1週間で約150g以上)。
- おむつが濡れる回数が1日6~8回以上ある。
- 赤ちゃんの便が黄色く、柔らかい。
赤ちゃんが泣く理由は、
空腹以外にも「抱っこしてほしい」「おむつが濡れている」「眠い」などさまざまです。
飲んだ直後で泣いているときは、空腹以外の理由も探ってみましょう。
母乳を増やすための方法7つ
1,赤ちゃんが欲しがるタイミングで与えましょう
赤ちゃんが泣いたり、口をパクパクさせたり、手を口に持っていくなどの
「お腹が空いたサイン」を見逃さないようにしましょう。
- 具体例
- 赤ちゃんが起きたタイミングや、ぐずり始めたタイミングで授乳をする。
- 授乳の間隔を決めすぎず、赤ちゃんが欲しがる頻度に合わせる
(1日8~12回以上が目安)。 - 夜間授乳も母乳分泌を促進するため、無理のない範囲で行う。
2,1日3食栄養バランスの良い食事
お母さんの栄養状態が母乳の質や量に影響します。
特にたんぱく質、鉄分、カルシウム、ビタミン類を意識しましょう。
- 具体例
- 朝食:ご飯、味噌汁(わかめ・豆腐入り)、焼き魚、ほうれん草のおひたし。
- 昼食:鶏肉の照り焼き、雑穀ご飯、野菜たっぷりのスープ。
- 夕食:豚肉の生姜焼き、ひじき煮、納豆、温野菜。
- 間食:ナッツ、ヨーグルト、バナナなど軽めのヘルシーな食品。
- 避けたい食品:脂っこいものや過剰な糖分の摂取は控えめに。
3,水分しっかり摂る(1日2L、授乳のたびに水分補給を)
母乳の多くは水分でできているため、授乳中は水分補給が特に重要です。
- 具体例:
- 1日2Lを目安に、
こまめに水やノンカフェインのお茶(麦茶、ルイボスティーなど)を飲む。 - 授乳のたびにコップ1杯の水を飲む習慣をつける。
- 水分補給が面倒な場合は、保温ボトルに温かいお茶を用意しておくのも良いです。
- 1日2Lを目安に、
4,乳腺マッサージ
乳腺を刺激することで母乳の分泌が促されます。
授乳前やお風呂の後に乳腺マッサージを行うと効果的です。
- 具体例:
- お風呂の中で、温かいタオルを胸にあてて乳腺を温める。
- 指の腹を使って、乳房の外側から乳首に向かって優しく円を描くようにマッサージする。
- 助産師や母乳育児の専門家に指導を受けると、正しい方法を学べます。
5,授乳姿勢を安定させる
赤ちゃんが乳首を深くくわえることで、効率よく母乳を飲めるようになります。
- 具体例:
- 授乳クッションを使用して赤ちゃんを安定させる。
- 横抱き、フットボール抱き、縦抱きなど、赤ちゃんとお母さんに合った姿勢を試す。
- 赤ちゃんの口が乳首全体を覆うようにし、乳首の先端だけをくわえていないか確認する。
6,赤ちゃんとスキンシップを増やす
スキンシップを増やすことで、オキシトシンの分泌が促進され、母乳分泌が増える効果があります。
- 具体例:
- 赤ちゃんを抱っこして肌と肌が触れ合う「カンガルーケア」を行う。
- お風呂の中で赤ちゃんと一緒に湯船に入る。
- 赤ちゃんの体を優しく撫でたり、話しかけたりする時間を増やす。
7,肩まわり、背中、足首を温める
体が冷えると血流が悪くなり、母乳分泌に影響します。
特に肩まわりや背中を温めることが大切です。
- 具体例:
- 温かいお風呂にゆっくり浸かる(シャワーだけで済ませない)。
- 冷え防止のため、靴下を履いたり、腹巻を着用する。
- 肩や背中にホットパックや湯たんぽを当てる。
- 冬場は温かい飲み物(生姜湯、白湯)を取り入れる。
産後の睡眠不足と慣れない育児の中で、完璧にやることは難しいかもしれません。
できることを心がけてみましょう。
母乳が出なくても大丈夫!
母乳が出ないことは決して「ママのせい」ではありません。
母乳の分泌には、個人差や様々な要因があり、責められるものではないのです。
分娩が難産だったり、出産後に大きなストレスや体調不良がある場合、ホルモンの働きが乱れて母乳が出にくくなることがあります。
生まれつき母乳分泌が難しい体質の人もいます。
しかし、母乳ではなくても、粉ミルクや混合授乳などの手段があります。
赤ちゃんに必要な栄養を与えることが一番大切です!
母としての愛情は赤ちゃんにちゃんと伝わっているのです。
ミルク育児のメリット5つ
冒頭部分の表でもあるように、
母乳とミルクそれぞれにメリットがあります。
こちらでは、ミルクのメリットについて、補足していきます。
1,母親の負担を軽減できる
母乳育児は母親の体調や生活に大きく影響します。
でも、ミルク育児であれば、母親以外の家族も哺乳瓶でミルクをあげることができるので、母親の負担を分けることができるのです。
特に、仕事復帰後や体調不良の時に役立ちます。
2,栄養バランスが整っている
現代の粉ミルクは、赤ちゃんに必要な栄養素(タンパク質、脂肪、ビタミン、ミネラルなど)が科学的に調整されています。
一部の製品では、母乳に近づけた成分(DHAやオリゴ糖など)も含まれており、
赤ちゃんの成長をしっかりサポートします。
3,授乳スケジュールが調整しやすい
ミルク育児では、授乳の間隔や量を記録しやすく、赤ちゃんの摂取量をはっきりと把握できます。
また、授乳間隔が約3時間ごとになるので、スケジュールを立てやすいこともメリットです。
4,母乳に問題がある場合の代替手段
母乳が出にくい、母乳育児が難しい場合(例えば、母親が服用中の薬が母乳に影響する場合)があります。
そこで、ミルク育児が、安全で有効な選択肢となってくれます。
5,家族の絆を深める機会
父親や祖父母など、家族全員が授乳に参加できるため、育児を通じて家族の絆を深める機会になります。
ミルクをあげているときは、みんな優しい表情になり心も和みます。
赤ちゃんも母親だけでなく家族の愛情を感じることができると思います。
ミルク育児の安全性と注意点
ミルク育児を行う際には、調乳の衛生管理や保存方法など、安全性に配慮することで赤ちゃんに安心して与えることができます。
1,適切な粉ミルクを選ぶ
赤ちゃんの月齢に合った粉ミルクを選び、パッケージに記載された指示に従って使用しましょう。
国内で販売されている粉ミルクは厳しい基準をクリアしており、安全性が確保されています。
2,調乳時の衛生管理
・粉ミルクを作る際は、哺乳瓶や乳首をしっかり消毒し、清潔な環境を保つことが重要です。
赤ちゃんがくわえる部分を素手で触らないように気を付けます。
・調乳には70℃以上のお湯を使用し、粉ミルクに含まれる細菌を殺菌するようにします。
流水や、ボールに冷水をため中で、40℃くらいになった状態のものを与えるようにしましょう。
哺乳瓶の乳首がつかないように、手の甲に垂らして、熱すぎず冷たすぎない人肌程度の温度がちょうどいいです。
3,適切な保存方法
調乳後は、できるだけ早く授乳を済ませるようにし、飲み残しは廃棄します。
また、粉ミルクの缶などは湿気や直射日光を避けて保存し、
開封後はパッケージに記載された期限内に使い切るようにしましょう。
4,赤ちゃんの反応を観察する
ミルクを飲んだ後に赤ちゃんが異常(アレルギー症状、便の変化、嘔吐など)を示す場合は、医師に相談してください。
アレルギー用ミルクや特殊ミルクが必要な場合もあります。
我が家の次男は、生後7か月頃、ミルクを飲むと下痢を繰り返しました。
受診すると、お腹が未発達なので、ミルクを消化しきれなかったそうです。

離乳食は続けてもらって大丈夫です。
ミルクは薄めて飲ませていきましょう。

ミルクを薄めて、栄養面や成長に問題はありませんか?

問題ないですよ。下痢にならないことが大事です。
焦らずに、少しずつミルクの濃度を戻していきましょう。
先生の指示に合わせて、ミルクとお湯の割合を変えていきました。
一か月ほどかけて、便の様子を見ながら濃度を戻していき、調子を整えることができました。
体重の増え方は、少し緩やかになるかもしれませんが、子供によって成長するペースはちがいます。

子供の成長は、長い目で見て対処していくといいと思います。
赤ちゃんに異変があったら、すぐに受診しましょう。
5,水の安全性
調乳に使う水は、ミネラルウォーターではなく煮沸した水道水を使うことが推奨されています。
ミネラルウォーターは赤ちゃんにとってミネラル濃度が高すぎる場合があります。
ミルク育児への切り替え方4つ
1,徐々に切り替える
最初から完全にミルクに切り替えるのではなく、1日の授乳のうち1回をミルクに置き換えるところから始めます。
赤ちゃんがミルクに慣れてきたら、少しずつミルクの回数を増やしていきます。
例えば、以下のように段階的に進めていく方法があります。↓
- 昼間の1回をミルクにする
- 夜の授乳もミルクにする
- 昼間のミルクの回数を徐々に増やしていく
母乳を完全にやめる場合、母乳を与える頻度を徐々に減らしていきます。
急にやめると乳腺炎のリスクがあるため、時間をかけて切り替えましょう。
2,授乳時の環境を整える
赤ちゃんがリラックスできる環境を整えましょう。
母乳からミルクへの切り替えは、赤ちゃんにとっても慣れない体験です。
静かで落ち着いた場所で授乳を行うと、赤ちゃんが安心しやすくなります。
3,母乳とミルクを混ぜる(必要に応じて)
赤ちゃんがミルクの味に慣れない場合は、母乳とミルクを混ぜて与える方法があります。
ただし、この場合は医師や助産師に相談しながら進めることをおすすめします。
4,適切な哺乳瓶と乳首を選ぶ
赤ちゃんが母乳からミルクに切り替える際に、
哺乳瓶の乳首の形状や素材が大きな影響を与えることがあります。
母乳に近い形状の乳首を選ぶとスムーズに移行しやすいです。
赤ちゃんの月齢に合った乳首(穴の大きさや柔らかさ)を選ぶことも重要です。
- ミルクを飲むのにかかる時間は、量や赤ちゃんの個性によって違いますが、10分~20分ほどが目安です。
- 赤ちゃんは一つの乳首になじむと新しい乳首を嫌がることがあるため、2個以上の乳首を交互に使いましょう。
歯並びにつながる哺乳のポイント3つ
はじめに(母乳の飲み方を意識する)
適切な哺乳瓶を選び、哺乳の姿勢を意識することで、将来の歯並びや口腔の健康に良い影響を与えることができます。
<赤ちゃんが母乳を飲むときの様子>
・乳首を深くくわえている
(乳輪の外側が見えなくなるくらい大きく口を開けている)
・舌を波上に動かす
・上顎のくぼみに押し付けて絞り出している
このように、
母乳を飲む赤ちゃんは、舌をしっかり動かし、口の機能を鍛えるトレーニングができています。
そのため、哺乳瓶で飲む際も、できるだけ母乳を飲むときと同じような飲み方ができることが大切です。
1,哺乳瓶の選び方
口を大きく開けられることが大前提です。
ピジョン:母乳実感↓
やわらかくて飲みやすいので、なかなか飲んでくれないときにもおすすめです。
我が家の息子たちもピジョンを使っていました。成長に合わせて、人口乳首のサイズを交換していくようにしましょう。
慣れてきたり、飲むのが速すぎたら、かための人口乳首の哺乳瓶を選ぶと、口のトレーニングになります。
2,人口乳首の交換時期の目安
出すぎる哺乳瓶はやめましょう
・下に向けただけでポタポタ垂れてしまうもの
・早く飲み終わってしまうもの
・人口乳首の先が裂けて劣化していることもあるので注意!
出すぎる哺乳瓶は、赤ちゃんががんばらなくても飲めてしまいます。
口の筋トレにならないので良くありません。
筋肉を鍛えるためにも、哺乳時間が10分以上かかることを目安にしましょう。
3,哺乳時の姿勢
水平に寝かせて飲ませるのは良くありません
嚥下の癖がついてしまう恐れがあります。
(舌が下がったまま飲み込む癖、口呼吸につながる恐れがあります)
<姿勢のポイント>
・頭がのけぞらないようにする
・水平に倒しすぎない
・足をだらんとさせないこと(下半身を安定させる)
・お腹の中にいるときと同じ、まん丸スタイルを意識する
哺乳の際、赤ちゃんの姿勢を意識してミルクをあげましょう。
赤ちゃんが哺乳瓶を嫌がるときの対処法9つ
哺乳瓶を嫌がる赤ちゃんも少なくありませんが、
以下の方法を試すことで慣れてもらえる可能性があります。
1.タイミングを工夫する
赤ちゃんが空腹すぎると、哺乳瓶を嫌がることがあります。
空腹すぎないタイミングで試してみると、少しずつ受け入れてくれることがあります。
2.母乳のにおいを減らす
母乳育児中の母親が哺乳瓶を使おうとすると、赤ちゃんが母乳のにおいを感じて哺乳瓶を嫌がる場合があります。
その場合は、他の家族(父親や祖父母など)に哺乳瓶でミルクを与えてもらうと、受け入れやすくなることがあります。
3.乳首の種類を変える
哺乳瓶の乳首の形状や素材が赤ちゃんに合わない場合があります。
複数の種類を試して、赤ちゃんが吸いやすいものを見つけてください。
特に、母乳に近い柔らかい乳首が好まれることが多いです。
4.ミルクの温度を調整する
ミルクの温度が適切でないと赤ちゃんが嫌がることがあります。
母乳と同じくらいの温度(37〜40℃程度)に調整して与えてみましょう。
5.遊び感覚で慣れさせる
授乳時以外のタイミングで哺乳瓶を赤ちゃんに持たせてみたり、口元に軽く触れさせたりして、哺乳瓶に慣れさせる時間を作ってみることも良いと思います。
6.少量から始める
最初は哺乳瓶に少量のミルクを入れて試し、赤ちゃんが飲みやすいようにします。
無理に飲ませようとせず、赤ちゃんが自分で吸うのを待つ姿勢が大切です。
7.赤ちゃんの気分に合わせる
赤ちゃんが機嫌の良いときに哺乳瓶を試すと、受け入れやすいことがあります。
逆に、眠いときや機嫌が悪いときは避けましょう。
8.赤ちゃんの体調を確認する
哺乳瓶を嫌がる原因が体調不良(口内炎や風邪など)の場合もあるため、
必要に応じて医師に相談してみましょう。
9.無理に進めない
無理に哺乳瓶で飲ませようとすると、赤ちゃんがますます嫌がる場合があります。
焦らず、赤ちゃんのペースに合わせることが大切です。
助産師や育児相談窓口に相談することで、より具体的なアドバイスを得られる場合があります。解決策が見つかるかもしれません。
粉ミルクの種類4つ
日本で販売されている粉ミルクは、赤ちゃんの栄養ニーズに合わせて設計されており、安全性が確保されています。
主に以下の種類があります↓
- 通常の粉ミルク
- 生後0ヶ月から1歳頃まで使用可能な標準的なミルクです。
- DHA、オリゴ糖、鉄分、カルシウムなどが含まれており、母乳に近い成分が配合されています。
- 主なブランド:明治「ほほえみ」、森永「はぐくみ」、アイクレオ「バランスミルク」など。
- フォローアップミルク
- 生後9ヶ月頃から3歳頃までを対象としたミルクです。離乳食で不足しがちな栄養素(鉄分やカルシウムなど)を補います。
- 主に離乳食が始まった後の栄養補助として使用します。
- アレルギー対応ミルク
- 牛乳アレルギーの赤ちゃん向けに作られたミルクです。
- たんぱく質を分解した「低アレルゲンミルク」や「アミノ酸ミルク」などがあります。
- 必ず医師の指示のもとで使用してください。
- 液体ミルク
- 常温で保存でき、調乳の手間が省けるミルクです。
- 災害時や外出時に便利ですが、コストがやや高めです。
ミルクの選び方ポイント3つ
- 赤ちゃんの月齢に合ったミルクを選ぶ
- 生後0ヶ月〜6ヶ月までは通常の粉ミルクが基本。
- 離乳食が始まる生後9ヶ月以降はフォローアップミルクを検討。
- アレルギーの有無を確認
- 医師と相談し、必要に応じてアレルギー対応ミルクを使用。
- ブランドや成分を比較
- どのブランドのミルクも栄養バランスは整っているため、赤ちゃんの好みやご家庭の予算に合わせて選びましょう。
ミルクの作り方
- 手を清潔に洗う
- 調乳前に必ず手を洗い、哺乳瓶や乳首を消毒します。
- お湯を準備する
- 粉ミルクは70℃以上のお湯で溶かす必要があります。やかんや電気ポットでお湯を沸かし、少し冷まして70℃にします。
- 粉ミルクを計量する
- 粉ミルクの缶に記載されているスプーンを使い、正確に計量します。
- 例:1杯(約2.7g)で20mlのミルクを作れる場合、120ml作るなら6杯分を計量。
- お湯を注ぐ
- 哺乳瓶に必要量の粉ミルクを入れた後、70℃以上のお湯を半分ほど注ぎ、しっかり混ぜます。
- 冷ます
- 残りのお湯または冷水を加えて、適温(約37〜40℃)に調整します。
- 手首の内側にミルクを垂らしてみて、熱くないことを確認してください。
ミルクの保存方法
- 作り置きは避ける
- 調乳したミルクは基本的に2時間以内に飲ませてください。
早めに飲ませてあげましょう。 - 飲み残しは細菌が繁殖する可能性があるため、再利用せず廃棄します。
- 調乳したミルクは基本的に2時間以内に飲ませてください。
- 粉ミルクの保存
- 開封後の粉ミルクは湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい場所で保管します。
- 開封後は1ヶ月以内に使い切るようにしましょう。
- 外出時の保存
- 外出先での授乳には、調乳済みのミルクを保温ポーチで保管し、2時間以内に与えます。
- または、粉ミルクとお湯を別々に持参し、必要なときに調乳する方法もおすすめです。
一回の授乳量と授乳間隔の目安(粉ミルクの場合)
| 月齢 | 一回の授乳量(目安) | 授乳回数(1日) | 授乳間隔 |
|---|---|---|---|
| 生後0〜1ヶ月 | 80〜120ml | 7〜8回 | 約3時間 |
| 生後2〜3ヶ月 | 120〜160ml | 6〜7回 | 約3〜4時間 |
| 生後4〜5ヶ月 | 160〜200ml | 5〜6回 | 約4時間 |
| 生後6ヶ月〜 | 200〜240ml | 4〜5回 | 約4〜5時間 |
| 生後9ヶ月〜 | 離乳食が主になるため授乳量が減少。授乳は1日3〜4回程度。 |
赤ちゃんの成長や食欲によって授乳量や間隔は異なります。
目安を参考にしながら、赤ちゃんの欲しがる量を優先してください。
授乳後にミルクを飲み残したり、吐き戻したりする場合は、量を調整する必要があります。
母乳育児にこだわりすぎない考え方6つ
- 母乳育児だけが「良い母親」ということではない
- 母親の心身の健康が最優先
- 家族全体の育児への参加が可能になる
- ミルク育児でも赤ちゃんは健康に育つ
- 可能であれば、母乳育児とミルク育児を併用する選択肢もある
- 他人の意見に振り回されなくてよい
- 母親がリラックスできる
睡眠不足や授乳に対するプレッシャーが軽減され、育児全体を前向きに楽しむことができます。 - 赤ちゃんが安心できる
母親が穏やかな気持ちで接することができるようになると、赤ちゃんも安心して育つことができます。 - 柔軟な育児が可能な場合もある
家庭や母親の状況に応じて、ミルクや混合育児など多様な方法を選ぶことができます。
母乳育児とミルク育児を併用する「混合育児」は、母乳のメリットを活かしながら、ミルクの利便性を取り入れる柔軟な方法です。
例えば、昼間は母乳、夜間はミルクを使うことで、母親が十分な睡眠を確保することができます。
このように、母乳とミルクをバランスよく取り入れることも一つの選択肢です。
最後に伝えたいこと
「母乳じゃないとダメ」
「完璧にやらないといけない」と思い詰める必要はないのです。
思いつめてしまうのは、
生まれてきてくれた大事な赤ちゃんのためですよね。
でも、育児において、正解はひとつとは限りません。
人それぞれだから、完璧をめざすのではなく、自分と赤ちゃんに合ったやり方を探していきましょう。
例えば、育児相談窓口を利用したり、家族やパートナーと話し合うことで、いい方法が見つかることもあります。
育児は、赤ちゃんと母親が一緒に成長していくものだと思います。
悩んで遠回りしていたとしても、前に進んでいるのです。
赤ちゃんが安全で、母親ができるだけリラックスして育児ができるように、ミルク育児を選択して取り入れることは、とても素敵なことです。
母乳でもミルクでも子供は育ちます!
自分が選んだ育児方法に自信を持ち、赤ちゃんと過ごす時間を大切にしていくことが幸せにつながっていくのだと思います。
焦らず、無理せず、赤ちゃんとの時間を大切にしてくださいね。
☆最後まで読んでくれてありがとうございます☆